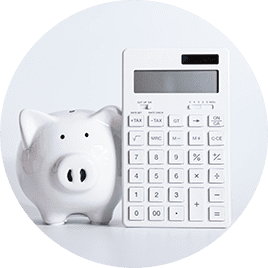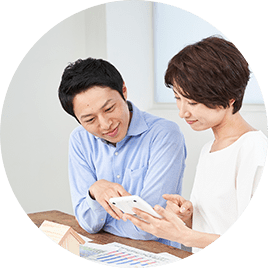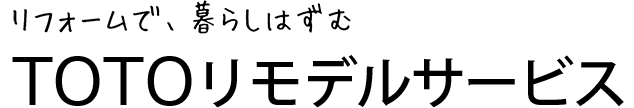「 間柱(まばしら)とは 」壁の下地探し(住宅建築 用語解説)
壁に棚などを付ける場合、壁の内部にクギやネジを打つための下地として「間柱」や「合板」が必要になってきます。
間柱は、木造や鉄骨造に必要な部材(二次部材*)の1つで、柱と柱の間にある小柱のことをいいます。
基本的に、木造も鉄骨造も間柱の使い方は同様です。
間柱に使われる材質としては、木材(木質の集積材)のほか、コの字型をした軽量鉄骨があります。
*二次部材とは・・・柱と梁のように鉛直力と地震力を負担させず、柱と梁に力を伝達させる目的や、局部的な力が発生する箇所に配置する部材を二次部材と呼びます。間柱は家の構造を支える柱ではなく、壁を支えるための柱です。
鉄筋コンクリート造のマンションなどの場合、住戸間の壁(戸境壁)はコンクリート壁ですが、住戸内のリビングとキッチンなど、部屋を分けている間仕切り壁にも間柱はよく使われています。
間柱を入れると壁の中に隙間をつくれるので、電気の配線を通したり、給排水管を間柱に固定することができます。
壁に棚などを付ける場合、クギやネジを打ち込む必要がありますが、石膏ボードや合板にクギやネジを打ち込んでも、すぐに抜けてしまいます。間柱に打ち込むことでクギやネジが抜けにくくなります。
壁に荷重のかかる棚等を付ける場合は、間柱の有無を調べることが大切です。

間柱のサイズ
幅30~50mm、奥行き 通し柱に合わせる
間柱は、外壁や下地材を釘で留めます。釘が打ち込める程度の幅、奥行きが必要となります。
角型鋼管又はH形鋼の場合 100×50mm ~ 200×100mm程度
木材の場合 一般的な大きさ 幅 30mm・奥行き 40~45mm
軽量鉄骨の場合 一般的な大きさ 幅 30~50mm・奥行き 40mm
ただし、建物の規模や天井の高さによって大きさは変わります。
また壁受け以外の用途で間柱を使う場合、上記より大きくなることもあります。
詳細なサイズは計算により間柱断面を決めます。
間柱の間隔
間柱は一定の間隔で配置されることがほとんどです。基本的には一尺(303mm)ごとに配置されます。
左右に一定の間隔で見つけることができます。
垂直方向は、基本的に床から天井まであります。
間柱の位置の調べ方
壁をコンコンとノックしてみて、音が響かないところが間柱の位置です。
市販品の「下地探し針」という道具を使って探す方法があります。
間柱部分に刺すと間柱にあたって止まる手応えがあります。「下地探し針」には深さがわかる目盛りがついています。一般的な石膏ボードの厚みの12.5mmに近い数値で目盛りが止まったら、間柱が入っている可能性があります。

下地探し針
市販されているので、簡単に入手できる「下地センサー」があります。
センサーを壁に沿わせて左右にスライドさせて、間柱部分を感知すると音や光で知らせてくれます。
下地の状況によって間柱が深い位置にある場合があり、その場合は感知できない可能性があります。検知できる深度が2種類から選べるなど、様々なタイプがあります。
建物によって間柱の種類や配置などが微妙に異なります。
万が一、クギ等を間違った場所に打つと配線を傷つけ、感電の恐れもあります。コンセント周りには配線も多いので、その周りにクギ等を打つのは避けた方が無難です。失敗すれば壁に不要なクギ穴を開けてしまうことになります。
可能であれば、コンセントをユニットごと外し、その穴から内部を覗いて壁の中を確認してみると安心です。